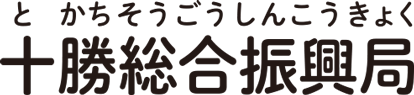防災マスターの体験した災害(水藤2)
阪神・淡路大震災で学んだこと 水藤 恒彦(帯広市) 2010.4.5

【はじめに】
平成7年1月17日、朝7時30分ごろ、自宅でNHKテレビのスイッチを入れた。
当時、帯広市消防本部予防課の課長補佐だった私は、災害現場はいろいろと体験しているので、多少のことでは驚
かないのだが、しかし、なんだこれは!!ヘリコプターから写し出される画面には、神戸市街の上空に、イクスジ
もの黒煙が、そして崩壊しているビルや家屋が、高速道路の倒壊している姿も・・・・・。
そのときのアナウンサーの声は、死者数は7人だった。
何、7人。私は、各種災害現場に赴いた体験から、そんな馬鹿な!!!恐らく1,000人以上ではと。
それから3週間後、私は神戸の土を踏んだ。大震災の実態を、そして、十勝にも来るであろう巨大地震の喚起のた
めにも。
【犠牲者の実態】
「ピカーッ」と空が光ったとたん「ドーン」という、深い地の底から突き上げるような上下運動に続いて「ぐらぐらっ、ばり
ばりっ」という揺れが、30秒続いたという。
平成7年1月17日午前5時46分52秒、ここから恐怖と惨劇が阪神淡路地区を襲ったのである。
あれからもう15年。阪神・淡路大震災の犠牲者は、6,433人。平成20年の全国1年間の交通事故での死者は、
5,155人。この数字は、一体なにを意味するのか?まさに、短時間で阪神・淡路大震災は多くの命を失ったのだ。
死者の6,433人の内訳は、半数以上が65歳以上のお年寄りで、さらにそのうちの半数以上が女性だった。このこと
は、災害弱者としてのお年寄りがいかに多かったか物語っている。
この原因は、神戸は第二次世界大戦で空襲を受け、焼け野原になったことにより、昭和20年・30年代の木造の古
い建物が多く、住人も1人暮らしの高齢者の女性が多かったのである。
そのような建物の倒壊により、高齢者の女性が犠牲となったのだ。
また、20歳から25歳の年代層からも多くの死者が発生している。 神戸は、大学、専門学校が多く、全国または世
界から学生が集る。古いマンションは倒壊する割合が高く、犠牲者が多い傾向となったのである。
このことは、平成54年に宮城県沖地震が発生し、死者16人の犠牲者がでた。この地震を教訓に、昭和56年6月に
建築基準法の改正が行われ、建物の耐震強化がされたのである。阪神・淡路大震災の倒壊家屋の殆どが昭和56年
以前の建物であった。
6,433人の死因では、その8割が倒壊した家屋の下敷きになったり、家具調度品が倒れたりした結果の圧死で、残
りの2割が焼死である。
【自助・共助の必要性】
地震直後、約20万人の方々が崩壊した建物に閉じ込められた、そのうち約80%の16万人は、自力又は家族に
よって脱出・救助された。15%の3万人は町内会または近隣の人たちにより救助され、残りの5%の1万人は、消防、
警察などの公的機関(公助)により救助された。
しかし、町内会等での救助では、生存率が非常に高く90%の人が生存した。しかし、公助が救助した生存率は
50%ほどであった。
なぜなら、これらの公助機関の救助チームは、東京、大阪、広島などから遠方から来るため、時間の経過とともに
手遅れになったことである。このことから、一番大事なことは、いかにして自分の命を守る、家族の命を守る「自助」で
ある。それとともに、15%の数字が示すように、近隣の人たちとの助け合いとなった自主防災の「共助」の精神であ
る。震災直後の「公助」は、まったくあてにできないのである。いや、動けないのである。

【地震直後の行動】
また、地震直後の行動は、一般に言われている「地震だ、火を消せ!」は、間違いないのだ。
まず、「自分の命を守る。家族の命を守る。」わずか30秒の揺れが収まるのを待ってから、火を消すなどの次の行動
を起こすこと。この帯広でも、平成5年1月15日の釧路沖地震のとき、揺れている最中にストーブの火を消しに行っ
て、ヤカンがひっくり返って大火傷。コンロの火を消しに行って、鍋がひっくり返り、大火傷。揺れている最中に玄関から
外に逃げようとしたところ、屋根の雪が地震の揺れで落下、頭に大怪我などなど。
人口17万人の帯広市で、火傷や怪我による救急出動が数多くあった。
【阪神・淡路大震災から学ぶこと】
阪神・淡路大震災の現場を実際に見て、特に北海道における地震の備えについて、4点ほど掲げる。
「1点目は、まず、家の耐震強度だ。」
前述したとおり、昭和56年の建築基準法の改正により耐震強化された建物はほとんど壊れていない。もし、昭和56
年以前の耐震強化されていない建物にお住みの方は、是非、建物耐震強度を信頼できる専門家の方に、耐震診断を
受けるとよい。
また、市町村でも相談窓口があるはずだ。耐震診断・耐震工事する場合、補助・融資をしている市町村もあると聞く。
特に恐ろしいのは、屋根に雪が10cm以上積もっているときは、雪の重さは数十トンある。
この破壊力は、阪神・淡路大震災での建物倒壊の比ではないかもしれない。
「2点目は、家具調度品の固定である。」
阪神・淡路大震災では、新築まもない家屋(耐震構造)で夫婦が寝ていたところ、タンスが倒れて夫が即死・・・。この
ような事例が数多くあった。タンスの転倒防止に、タンスの下にマットを置く。天井の間に、突っ張り棒を立てたりする固
定方法があるが、震度6・7では効き目は有効ではない。金具等で固定するのが最適である。ただし、壁のボード等に
おいては、壁の中に空洞部分があるので要注意。
「3点目は、寒さ対策である。」
神戸が震災に見舞われたのは、1月17日午前5時46分。その時の気温は、+1℃。帯広で同月、同時間であれ
ば、-25℃でも不思議ではないはず。もし、家屋が倒壊し、家の下敷きになり寝間着のまま、梁にはさまれたら、おそ
らく30分で凍死ではないだろうか。裸足で5分間、外に出たら凍傷で両足切断。また、避難所に避難しても停電によ
り、ボイラー停止、暖房はなし。寒さ対策は、北海道の厳寒期における重要な課題である。
「最後の4点目は、トイレ対策である。」
午前8時、避難所には500人ほどが避難してきた。しかし、断水でトイレの水がない。避難所には仮設トイレはない。
人間、朝になると・・・・。避難所は、当初まさに糞尿の大汚染になったといわれている。
食べること、飲むことはある程度、我慢できる。しかし、避難所ではトイレパニックが発生することは必然である。
以上4点挙げた。
家屋の耐震強化、家具調度品の固定、寒さ対策、トイレ対策その解決策は?
自分の命、家族の命を守るのは、あなたです!!!
阪神・淡路大震災では、大勢の方が地震で亡くなりました。1回の地震で6,433人ではありません。1人が死んだ地
震が6,433回あったのです。災害時の人間の行動には、一つとして同じものがないからです。
このメッセージが阪神・淡路大震災の教訓として、少しでもお役に立てば幸いです。