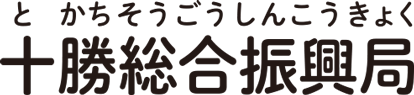防災マスターが体験した災害(長内)
いつまでも記憶に残る『釧路沖地震』(昭和27年3月4日発生) 2010.4.5
大正2年2月20日の浦河沖地震から平成5年1月15日の釧路沖地震まで、帯広を中心とする震度4以上の地震は
約30回を数えています。
なかでも、M8.0以上のものは4回を数えていると池田町史にも記されています。
なかでも、十勝にとって記憶から消えない大地震は、昭和27年3月4日午前10時23分の「十勝沖地震」です。
当時は戦後の復興のなかで、財政支出に困窮しているときに起こった災害でした。
更に、平成5年1月15日の釧路沖地震は大規模なもので、道東一円に大被害をもたらしました。
このなかから、私の記憶に残っている十勝沖地震で、感動したことを交えて綴ってみました。
昭和27年と言えば、私は地元高校を卒業して地元の中学校に奉職して1年目の終わりを迎えようとする春の3月4
日のことでした。
平常であれば普通日であったので、きっと生徒の前で授業をしていたでしょう。その時、もし地震がきたら生徒をどの
ように導いたらよいか、自分にその心構えは備わっていたのだろうか、そのときのことは思い出せません。
仮に高卒の19歳の若造を、非常時の安全指導マニュアルで訓練していたとしても、きっと慌てふためいていたに違
いありません。想像しただけでもぞっとします。
幸いにも、その日は町内の教職員全員およそ150人が池田小学校に集まって大教室で研修会が開会されて間もな
くのことでした。大きな揺れ、長い揺れに、会場全体が踊っているような感じ。何か指示があったかどうか思い出せま
せん。大半の方は、会場南側の窓を開けて外にもんどりうって飛び降りたような気がします。
外には、まだ雪があり地面は固く、歩くことは出来ましたが、窓の端には昔地面に建てた梯子に土管を縦に繋いだ外
煙突が、窓から外に飛び降りて行く人の頭の上に飛び散り、危ない場面を目の当たりにしました。
しかし、殆どの方が窓から外に避難したはずなのに、会場(教室)の前方角に、大きなダルマストーブの倒れるのを
抑えるかのようにしている方が一人おられた。この方は、今は亡き大石忠夫先生であった。もう窓の外には誰もいな
い。もしも、ストーブが転倒したら池田小学校は木造で古い建物であり、きっと全焼したことでしょう。
地震の揺れも止まって、私も窓から外に出て、自分の家に向かいました。足をとめて周囲を見ると、校舎西側の堤防
の上を走っている方もいました。地震で堤防にひび割れが生じたとき、そこに人が落ち込んで、非常に危険であるとい
います。
しかし、こんな慌てふためいているときに、目の前が安全に見えたら構わず急いで走ってしまうのである。
自分の家までの約1kmの間、周囲の状況はどうであったか、今では思い出すことは出来ません。
家に着いたら家の中は惨たんたるもの、家財道具は倒れ、出来たての漆喰壁はみな剥がれ落ちて、敷いたばかり
の青畳は、片隅も見えず、手のつけようもない状況でした。
入居した住宅は、池田町の最初の公営住宅で、新しい住宅に入居させてもらって感激も一入でありましたが、思わ
ぬ大地震を被災して、家は頑強で崩れはしなかったものの、家の中は大きなゴミ箱状態。あまりにも荒れた様子を見
て、初めて地震の怖さを思い知らされました。
さて、その日その時、大きな災害と出会った時に、今ここにいて自分はどんな行動をとることが最善なのかを咄嗟に
判断して、責任ある行動をしなければならにということを、今は亡き大石忠夫先生から無言の大きな教訓として自分の
体に刻み込み、行動することを誓って稿を終わります。