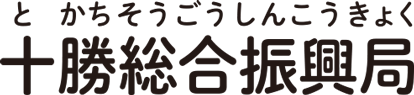第1回 北海道の管理河川の川づくりワーキング
日時 平成27年11月4日(水) 14:00~16:00
場所 帯広建設管理部 A会議室
|
第1回北海道の管理河川の川づくりワーキングが、平成27年11月4日(水)に実施されました。
帯広建設管理部から、帯広川(中流地区、ウツベツ川地区、柏林台川地区)、伏古別川、居辺川砂防区間、居辺川河川区間、渋山川について、それぞれ事業の必要性、事業目的、事業内容(案)、環境対策(案) などを説明しました。居辺川・渋山川へこれまで寄せられた意見等の回答内容説明を行ったのち、ワーキングメンバーによる意見交換を行いました。
注意)資料や議事内容については、事務局にて一部要約しています。
|
北海道の管理河川の川づくりワーキングのメンバー(今回の欠席者を含む)
|
団体名
|
氏名
|
| NPO法人 十勝多自然ネット |
佐藤 美佐男 |
| NPO法人 日本野鳥の会十勝支部 |
室瀬 秋宏 |
| 浦幌野鳥倶楽部 |
武藤 満雄 |
| 帯広ウチダザリガニ・バスターズ |
鏡 坦 |
| 帯広川伏古地区子どもの水辺協議会 |
関川 三男 |
| 帯広市町内会連合会 環境衛生部会 |
金森 秀雄 |
| 川と河畔林を考える会 |
高倉 裕一 |
| 地球環境を守る十勝連絡会 |
平譯 正勝 |
| とかち帯広サケの会 |
千葉 養子 |
| 十勝川水系の生態系再生実行委員会 |
石垣 章 |
| 十勝川中流部市民協働会議 |
紅葉 克也 |
| 十勝川のシシャモを守る会 |
和田 宏樹 |
| 帯広建設管理部 事業課 |
山本 文昭 |
|
主な実施内容
1. 自己紹介
2.座長選出
3.事業説明
4.意見交換
意見交換における意見等
【帯広市街河川について】
• 柏林台川の水辺の楽校付近でニジマスの放流をしたことがある。この川の水は茶色で鉄分が多いように見える。水質はどうなのか。対策はあるのか。
• 特に帯広市街地を流れる川の治水対策は、早急にやるべきである。
• 環境保全も大事だが、柏林台川、伏古別川、帯広川などの水害の危険性には早急に対応してほしい。
• 治水安全度を高めるということは大枠で理解できる。帯広川や伏古別川については、市民の生命財産にかかわる緊急性があり、事業計画後のスピードアップをお願いしたい。
• 伏古別川では10年降雨規模の対策が実施されているはずが、H22、H23、H24と3年連続して計画高水位に達している。何が原因か確認して今後の事業に反映すべきである。
• 町内会の活動として、5月の第2日曜日の朝6時~7時に、全市一斉の河川清掃を実施している。今年は3,600人で実施した。最近はポイ捨てなどがほとんどなくなり、とてもきれいになった。川をきれいにし、水の流れをよくし、水害をなくす、ということを考えている。
• 帯広川で堤防などを整備するのなら、自転車道の整備との連携を図れないか、検討してもらいたい。需要はある。
• 水とのふれあい、魚道、自転車道や散策道、子供たちが安心安全に遊べる環境などを考えて整備してほしい。
【居辺川・渋山川について】
• 居辺川、渋山川では、なぜ河床低下が進行しているのか。いろいろな方策が成功しておらず、崩れが本川でも支川でも進行している。どういう手を打ったらこれまでの失敗を乗り越えられ、今後30年、50年とうまくいくのか。原因や方策について、資料や建設管理部の意見を確認したい。
• 渋山川について、同じ日高山脈を源として近くを流れる美生川や芽室川と、何が違うのか。川の性格、特徴、起きていること、歴史などについて、工学的な対処をするにあたりトータルな意味で検討すべき。
• 渋山川ではなぜ河床の砂礫層が薄いのか、そのヒントは上流の1号砂防ダムにある。現地で見て考えたい。
【生物・湧水について】
• 貴重な生物が確認されているので、その環境を保全しつつ環境に優しい工事を願う。
• 東京出身だが、十勝の川の魚の量には感動している。
• 魚類や底生生物などは、多少ダメージを受けても川の持つ能力に応じて時間をかけ回復する傾向にある。その回復を人の手で少し早めてやる、という工事の考え方もある。
• 魚類調査の方法や時期を教えてもらいたい。
• 魚の行き来を確保するための具体策は何か。
• 魚道をつくっても、どの魚が使っているのかの調査がないと「大丈夫」とはならない。調査を実施してほしい。
• 魚をその場所に留めるために、たまりや深みがある川を考えてほしい。
• 特に十勝川全体で少ないサクラマス(ヤマベ)について、考えながら工事を考えてほしい。
• 河床の湧水についての調査はされないのか。
• 湧水はザリガニとも密接な関係がある。その調査もしてほしい。
• ザリガニにとって、上流の工事や伐採はもちろん、下流・本流の工事も影響がある。大雨時、下流に流されたものは、生き残れば数十年をかけて上流、支流にのぼる。配慮してほしい。
• できる限り鳥の繁殖期を避けて、工事を実施してほしい。
• 鳥については種類によって、その場所に営巣環境があるのか、また、何を餌にしているのか、といったことが重要である。
※各メンバーの発言については、事務局にて一部要約しております。
|
ワーキング状況 1

ワーキング状況 2